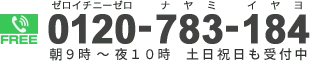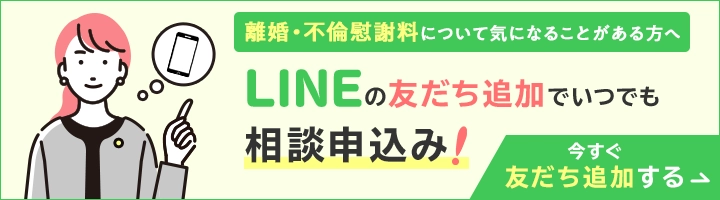共同親権で養育費はどうなる?すでに離婚している場合は?新ルールも解説

- 公開日:2025年3月11日
- 更新日:2025年03月11日
2026年までに施行される見通しとなった、離婚後の共同親権を導入する民法改正案では、離婚と子どもに関するさまざまなルールが変更されます。
そのため、「共同親権になったら養育費はどうなるの?」と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこのコラムでは、共同親権制度が導入されると養育費の取決めにどのような影響があるのか、わかりやすく解説します。
離婚を考えている方だけでなく、すでに離婚をされている方も、ぜひ最後までご覧ください。
目次
この記事を読んでわかること
\専門スタッフが丁寧に対応します!/
共同親権とは
「共同親権」とは、父と母の両方が子どもの親権(子どもを成人まで育てるために親が負う権利・義務)を持つ制度のことです。
現在の日本では、原則として結婚している父母にのみ共同親権が認められており、離婚後は父と母のどちらか一方しか親権を持つことができません(単独親権)。
しかし、子どもの利益の観点から、両親が協力して子育てに関わることを目的として、2024年に離婚後の共同親権を導入する民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正案は、2026年までに施行される見通しです。
そして、改正法のなかでは、親権や子どもの養育に関する新たなルールも設けられることとなりました。
共同親権になっても養育費の支払義務はなくならない
改正法で設けられた新たなルールのなかには、養育費に関するものも含まれます。
このルールは、子どもと暮らす親が養育費を受け取りやすくすることを目的としたものです。
そのため、今後も子どもと離れて暮らす親の養育費の支払義務がなくなることはありません。
つまり、改正民法の施行後にたとえ共同親権を選択したとしても、養育費を受け取れなくなることはないということです。
また、共同親権であることを理由に養育費の金額が増減することもありません。
単独親権・共同親権にかかわらず、養育費の金額は、父母の収入・職業、子の人数・年齢などによって決まります。
共同親権における養育費の新たな3つのルール
では、共同親権が導入される際、具体的にどのように養育費のルールが変わるのでしょうか。
変更される主なルールは、以下の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①「法定養育費制度」の創設
「法定養育費制度」とは、離婚するとき養育費の取決めをしなくても、離婚後に法律で定められた金額の養育費を請求できる制度です(改正民法第766条の3)。
養育費を請求するには、夫婦間の話合いや、裁判所を通した手続(調停・審判・裁判)で養育費の金額などを取り決める必要があります。
また、取決めをしていなければ、過去に遡って請求することはできません。
しかし、法定養育費制度が創設されることで、取決めを行わなくても離婚した日に遡って、取決めを行う(または子どもが18歳になる)までの間、法定養育費を請求できるようになります。
ただし、法定養育費の金額は、実際の収入など個別の事情を考慮せず一定の基準に基づいて決まるため、養育費算定表の金額よりは低額になる可能性があるでしょう。
②「先取特権」の付与
「先取特権(さきどりとっけん)」とは、法律で定められた一定の債権について、ほかの債権者よりも優先して弁済を受ける権利のことです。
養育費の請求権に先取特権が付与されることで、養育費の支払いが滞った場合に、優先的に相手の財産を差し押さえられるようになります。
また、通常、差押えをするには調停や審判などの手続で「債務名義(養育費の請求権があることを証明する法律で認められた公文書)」が必要です。
しかし、先取特権が付与されると、父母間で養育費の支払いについて適切に取決めた合意書があれば、債務名義なしに差押えができるようになります。
この先取特権は法定養育費にも及ぶとされており、養育費を回収するハードルがより低くなることが期待できるでしょう。
③養育費の差押え・情報開示手続の簡素化
調停や裁判で養育費を取り決める際には、父母の収入や資産をもとに養育費の金額を算定します。
そのため、養育費の支払義務がある親が収入・資産を開示しないと、養育費の取決めができません。
しかし改正民法の施行後は、家庭裁判所から当事者に対し、収入・資産の情報開示を命じられるようになりました。
また、養育費の差押えをする際には、裁判所に1回申立てをするだけで、以下の一連の手続を申請できるようになります。
- 財産開示手続
- 情報提供命令
- 債権差押命令
このように手続が簡素化されることにより、主に裁判において養育費の取決めや差押えがよりスムーズに行えるようになり、負担が軽減されます。
共同親権のもとで養育費を取り決める方法
共同親権となった場合でも、養育費を取決める方法はこれまでと同じです。
まずは父母間で話合いを行い、合意できなければ裁判所の手続である調停・審判(離婚前は「離婚調停」、離婚後は「養育費請求調停・審判」)で決めることになります。
取り決めるべき主な内容は、以下のとおりです。
- 養育費の金額
- 支払方法
- 支払時期
- 支払期間 など
なお、あとでトラブルにならないよう、取り決めた内容は書面に残しておきましょう。
強制執行力のある書面(公正証書・調停調書・審判書など)があれば、養育費が支払われない場合に相手方の財産を差し押さえることができます。
すでに離婚済で養育費を受け取れていない場合は?
すでに離婚している方で、養育費について取り決めていない場合、改正民法が施行されるまでは過去に遡って養育費を請求できません。
また、離婚するとき養育費の取決めをしている場合も、養育費の請求権は原則として5年または10年で時効にかかってしまいます。「いつか支払ってもらおう」と思っていると、損をしてしまうかもしれません。
そのため、養育費を受け取れずお悩みであれば、できるだけ早く養育費を請求すべきでしょう。
しかし、「元配偶者と連絡が取れない」「支払いを拒否されてしまった」など、スムーズに請求ができないケースも少なくありません。
そのような場合には、弁護士にご依頼いただくのがおすすめです。弁護士であれば、法的な知識や実務のノウハウを生かし、あなたがきちんと養育費を受け取れるよう交渉を進められます。
まとめ
離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されたからといって、養育費が受け取れなくなったり、養育費の金額が増減したりすることはありません。
むしろ、養育費に関する新たなルールが導入され、養育費の取決めや回収がしやすくなることも期待できます。
現在、すでに養育費が支払われず悩んでいるのであれば、できるだけ早く養育費を請求すべきでしょう。
ご自身では交渉が難しいケースでも、弁護士に相談することで解決できる可能性もあります。
アディーレ法律事務所なら、離婚後の養育費に関するご相談は無料です。離婚問題に精通した弁護士が、あなたのご状況に合わせて解決策をご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
\専門スタッフが丁寧に対応します!/
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 慶應義塾大学法学部
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。